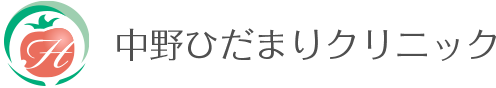- HOME>
- ピロリ菌検査・除去
ピロリ菌とは

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、1979年にオーストリアの研究者たちによって発見された、胃の粘液に棲みつき、ヘリコプターのようにひげの部分を回転させて移動する細菌です。発見した研究者たちは2005年にノーベル生理学賞を受賞しています。
衛生環境が悪い地域の、免疫力や胃酸が弱い乳幼児に感染が見られる場合が多く、2024年時点の日本で言えば、衛生環境の整っていない時代に乳幼児期を過ごした50代以上の世代に感染者が多い傾向があります。また、それより若い世代でも、乳幼児期に親を介して感染している可能性があります。
ピロリ菌は以下に挙げるような様々な病気の大きな要因の1つと考えられています。
- 慢性胃炎
- 萎縮性胃炎
- 胃潰瘍
- 十二指腸潰瘍
- 胃がん
- 胃ポリープ
- MALTリンパ腫
- 免疫性(特発性)血小板減少性(ITP) など
これらの中にはQOL(生活の質)を下げるだけでなく、進行すると命に関わるものも含まれています。こうした病気の予防・治療に高い効果を期待できるのが、ピロリ菌検査・除菌です。
ピロリ菌検査
ピロリ菌検査にはいくつかの方法があり、上部消化管内視鏡(胃カメラ)を使う検査もあれば、使わずに済ませられる検査もあります。以下ではそれらの中から代表的な方法を紹介します。
胃カメラを使った検査
培養法
胃カメラを通じて胃の粘膜の細胞を採取し、温度管理をしながら5〜7日間培養します。その後、培養された菌の形や状態からピロリ菌がいるかどうかを判断します。ピロリ菌に感染していないケースを見つけるために非常に有効な方法ですが、高い技術力が必要な検査でもあります。
迅速ウレアーゼ法
胃カメラで採取した胃の粘膜の細胞にピロリ菌が含まれている場合、専用の薬品を使って染めると菌が作り出すウレアーゼの影響で、色に変化が現れます。簡単かつ迅速に結果がわかるというメリットがある反面、除菌治療後の精度がやや劣るというデメリットがあります。
組織鏡検法
胃カメラを使って採取した細胞を染色し、100倍以上の顕微鏡で確認する検査です。同時に慢性胃炎の炎症を調べることもできますが、担当する医師の経験などに結果が左右されやすい傾向があります。
胃カメラを使わない検査
便中抗原測定
便検査によってピロリ菌の有無を調べる検査です。スピード重視の定性検査に加え、より正確に調べる精密検査もあります。除菌治療後は結果の精度がやや低下するというデメリットがあります。
尿素呼気法 (UBT)
専用の薬を飲んでいただき、服用前と後の呼気を集めることで、ピロリ菌の有無を診断することが可能です。非常に簡単に検査ができ、かつ高精度なことから、一般的な検査方法として採用されています。
ピロリ菌除菌治療

検査によってピロリ菌が見つかった場合は、ピロリ菌除菌治療に移ります。と言っても手術などが必要なわけではなく、PPI(プロトンポンプ阻害剤)という胃酸抑制剤や、クラリスロマイシン、アモキシシリン、メトロニダゾールといった抗生物質を1週間ほど服用することで除菌が可能です。
目指すのはピロリ菌の完全な死滅ですが、一度の治療では除菌しきれないケースもあるため、治療終了後1ヶ月の段階で改めて判定を行います。この際にピロリ菌の死滅が確認できない場合は、もう一度除菌を行うこともあります。
なお、除菌が成功すれば胃がんなどのリスクは大幅に減少しますが、絶対にそういった病気にならなくなるというわけではありません。除菌完了後も定期的に内視鏡検査などを受け、胃の状態をチェックしておくことが重要です。
ピロリ菌検査・除菌に保険が適用される場合について
ピロリ菌検査及び除菌治療は、条件を満たしている方であれば国民健康保険や社会保険などの公的な保険の適用を受けることができます。条件とは、胃カメラによる検査を受け、慢性胃炎(萎縮性胃炎)の診断を受けることです。
そのため、胃炎の自覚症状がなく、「親族に胃がんになった人がいるから、ピロリ菌検査を受けておきたい」という方の場合や、便中抗原測定のような胃カメラを使わない検査を受ける場合は、自費診療での受診となります。あらかじめご了承ください。
自費診療でのピロリ菌検査・除菌にも対応
通常、ピロリ菌の検査を保険適用で行う場合、胃カメラを使用して胃の状態を確認する必要があります。しかし、胃カメラを希望しない患者様や、単にピロリ菌について調べたいという方も多くいらっしゃいます。
そのため、中野ひだまりクリニックでは自費診療でのピロリ菌検査・除菌にも対応しています。
自費診療でのピロリ菌検査・除菌の費用
3,300円(税込)